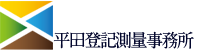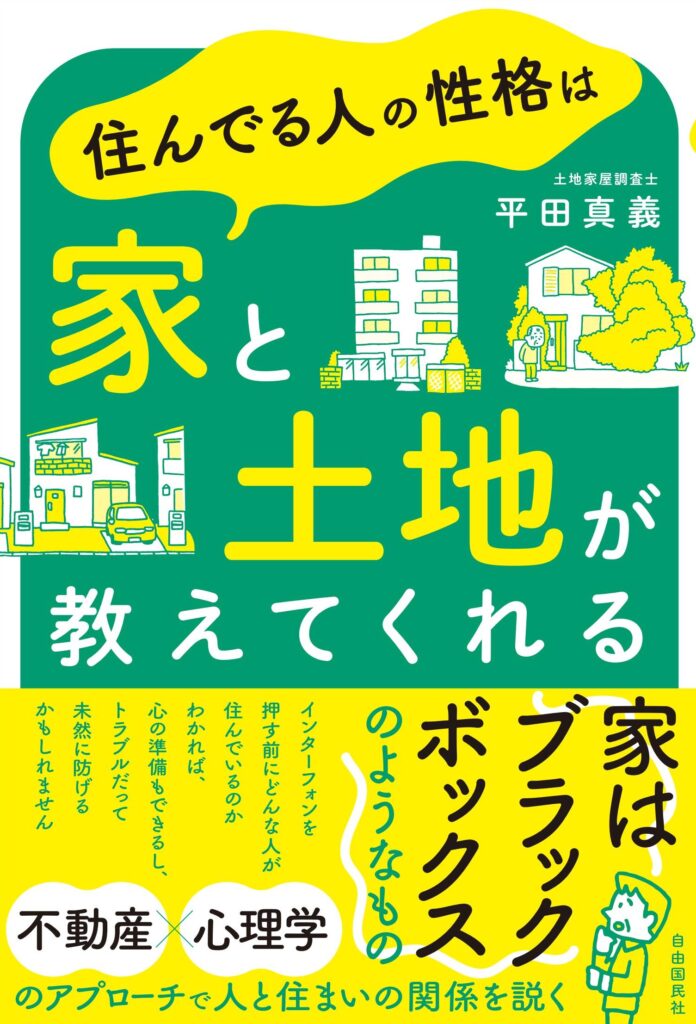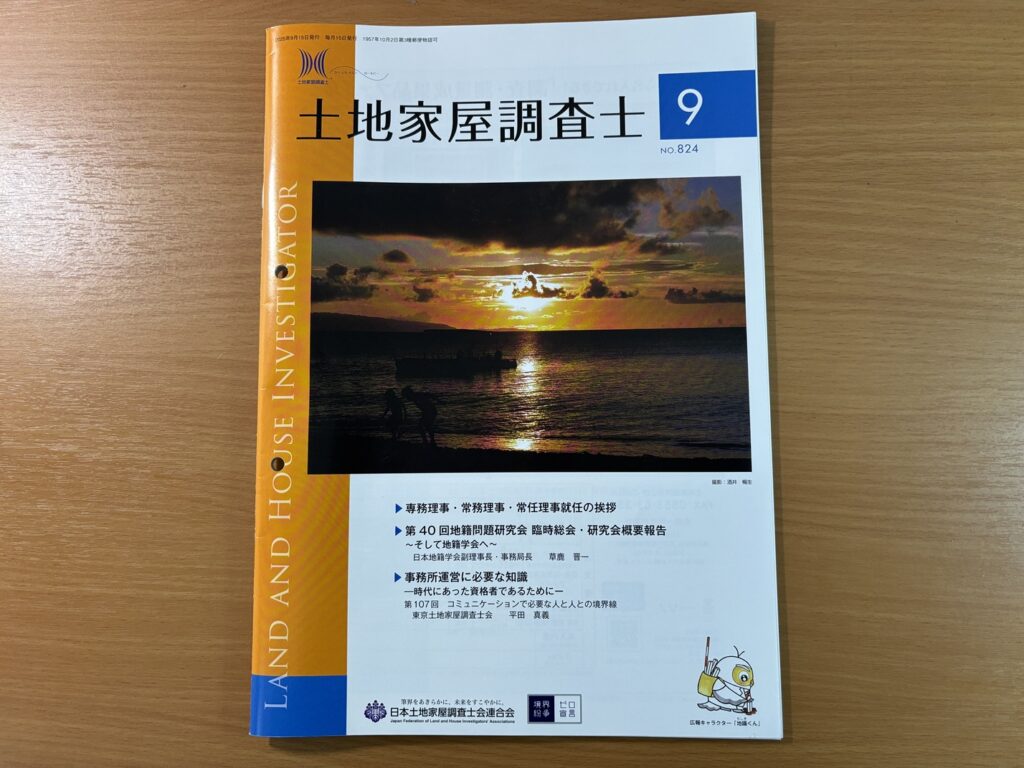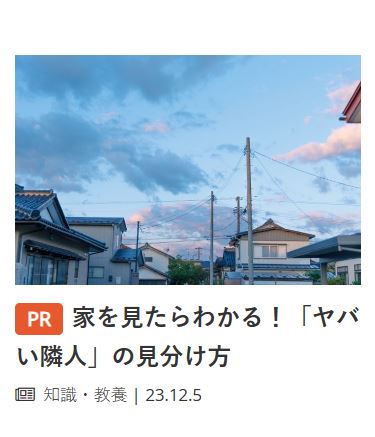測量調査のお困りごとを
平田登記測量事務所が
解決します
平田登記測量事務所では、土地や建物の測量・登記を行います。
相続に関する測量は後に残る配偶者またはお子様たちのためにも必要です。
苦労したからこそ、得たスキルが活きています


土地家屋調査士にとって近隣所有者さん達との対話は重要度の高いものです。土地家屋調査士は「測量」ができて当たり前ですが、全調査士が「コミュニケーション能力」に長けているとは限りません。私自身、近隣所有者へのアプローチには相当の苦労を要しました。
境界立会いの途中、ご近所さん同士が突然口げんかを始めてしまい、どうする事も出来なくなり、精神的に病んでしまった経験があります。それをきっかけに人の心理が知りたくなり、心理学を学び、「話す」より「聴く」が大切、というコミュニケーションスキルを身に着けました。
お陰様でこのスキルを業務やプライベートにも取り入れさせて頂き、好評を博しております。
お見積作成、受託。
市区町村役場にて
道路境界等調査、法務局の調査。
近隣所有者様へ
ご挨拶、調査、測量作業。
測量データ照合、官民打ち合わせ、
仮杭設置等。
関係所有者様の皆様と立会い、
了承後境界標設置。
官民及び民有地境界を確認した旨の書類の取り交わし。
完了後、納品。
よくある質問
- 測量業務のエリアはありますか?
-
より良いサービス提供のため、測量エリアを限定しております。
東京都は23区内・多摩地区と、埼玉県の一部地域(所沢市、狭山市、入間市、新座市、志木市、和光市、富士見市)が測量業務エリアです。その他のエリアについてはご相談ください。 - 本当に短期間で測量が終わるの?
-
近隣の方々のご意見も尊重しなければならない業務ですので、確約はできませんが、隣接所有者の方々には細心の注意を払いアプローチして参ります。進捗状況は逐一ご報告させて頂きます。
- 境界確認測量の期間はズバリどれくらいかかるの?
-
現場の規模、状況にもよりますが、最低2ヶ月~3ヶ月の期間を要しております。お取引日程がお決まりになられている方々には、お早めのご依頼をお願いしております。
- 測量費用のお見積をお願いしたいのですが、費用はかかるのですか?
-
当該地の不動産登記簿謄本、公図をご用意頂いた方に限り、原則的に無料でお見積させて頂きます。
WORK
NEWS
BLOG
-



相手の事を「わかろう」とするだけで、程よい対人距離になる
-



人を責めずに仕組みを責める
-



「思い通りにならない」ことを肯定してみる
-



人間関係が上手くいっていない人は、知らないうちに「なわばり」を侵している!?
-



「住まいが好き」=「家族が好き」
-



距離感を「測量」してみる
-



「空間」の大切さ
-



「共感」はOK!「同情」はNG!?
-



他人って価値観の違う人だらけなんですよね…
-



あえて「ムダ」なことをしてみる
-



人のこころは「不動産」に表れる
-



幸せな「なわばり」「スペース」とは?